創業1717年 地元民に愛される淡麗旨口の酒 牧之通りと青木酒造をめぐる旅/南魚沼市
2023年08月09日
いいね
11121ビュー
全国最多の酒蔵数を誇る日本酒王国にいがた、その酒蔵数は89蔵にも及びます。
それぞれの酒蔵には、酒造りに対してのこだわりが詰まっています。
今回は、南魚沼市塩沢の牧之通りと青木酒造を訪れました。
それぞれの酒蔵には、酒造りに対してのこだわりが詰まっています。
今回は、南魚沼市塩沢の牧之通りと青木酒造を訪れました。
青木酒造の仕込み水
旅の始まりは最寄りのJR上越線、塩沢駅を降りたところから。
田舎の駅舎という感じで、趣が感じられます。
駅からまっすぐてくてくと歩いて行くと青木酒造「鶴齢」の看板が見えてきます。
ここは青木酒造の裏口倉庫。
できたての酒がこの倉庫から搬出されていきます。
駅からまっすぐてくてくと歩いて行くと青木酒造「鶴齢」の看板が見えてきます。
ここは青木酒造の裏口倉庫。
できたての酒がこの倉庫から搬出されていきます。
酒蔵といえば、杉玉!!
立派に飾られていますね。
ちなみに酒蔵の杉玉は、「酒ができましたよ!」という蔵からの目印となっています。
おっと、その脇に何かありますね!
立派に飾られていますね。
ちなみに酒蔵の杉玉は、「酒ができましたよ!」という蔵からの目印となっています。
おっと、その脇に何かありますね!
青木酒造の仕込み水です!
酒は水が命。
仕込みから器具の洗浄など、全てこの仕込み水で酒蔵の仕事が行われているわけです。
この水は一般の方に開放されていますので、地元の人がタンクを持って汲みに来ます。
私も水筒に入れ、ゴクリ!
透明感があり、軟水寄りの味わい。この水で鶴齢が造られると思うと余計うまく感じます。
さらにてくてくと3分ほど歩いて行くと、突如目の前に出現するのは牧之通り(ぼくしどおり)、雁木通りの風情あふれる街並みが現れます!
酒は水が命。
仕込みから器具の洗浄など、全てこの仕込み水で酒蔵の仕事が行われているわけです。
この水は一般の方に開放されていますので、地元の人がタンクを持って汲みに来ます。
私も水筒に入れ、ゴクリ!
透明感があり、軟水寄りの味わい。この水で鶴齢が造られると思うと余計うまく感じます。
さらにてくてくと3分ほど歩いて行くと、突如目の前に出現するのは牧之通り(ぼくしどおり)、雁木通りの風情あふれる街並みが現れます!
まるで江戸時代にタイムスリップしたかのような街並み
この牧之通り、都市景観大賞「都市空間部門大賞(国土交通大臣賞)」(H23)と、「アジア都市景観賞」(H27)を受賞し、世界的にも評価されている街並みとなっています。
古くは江戸と越後(新潟)を結ぶ三国街道の宿場町として要所となっていた地域です。
かつては旅人や大名行列で人々が行き来していたことでしょう。
雁木通りを歩いていると、まるで江戸時代にタイムスリップしたような気分になってきますね。
古くは江戸と越後(新潟)を結ぶ三国街道の宿場町として要所となっていた地域です。
かつては旅人や大名行列で人々が行き来していたことでしょう。
雁木通りを歩いていると、まるで江戸時代にタイムスリップしたような気分になってきますね。
郵便局も木を基調とした外観。
この縦型の郵便ポストも今では珍しくなりましたよね。
細部にまで牧之通りのこだわりが見受けられます。
この縦型の郵便ポストも今では珍しくなりましたよね。
細部にまで牧之通りのこだわりが見受けられます。
私がいつもお世話になっている地元の金融機関、塩沢信用組合も昔の蔵を表した外観です。
中も用事がなくても入ってみたくなるような造りになっているので、ぜひ休憩がてら訪れてみてください。
さらに牧之通りにはカフェや飲食店もあります。
酒蔵への気分も高まって来ます、ワクワク!
中も用事がなくても入ってみたくなるような造りになっているので、ぜひ休憩がてら訪れてみてください。
さらに牧之通りにはカフェや飲食店もあります。
酒蔵への気分も高まって来ます、ワクワク!
歴史と風格のある酒蔵の佇まい
牧之通りを歩いていくとすぐにありました、青木酒造さん!
牧之通りの街並みに見事に調和した外観で、歴史を感じさせる蔵です。
青木酒造は一般の方には酒蔵見学は実施していません。
写真も外部公開は不可ということなので、言葉に綴ります。
今回、酒の心は特約店契約をしていただいているので、特別に中を案内していただきました。
現在の蔵の方針は「徹底した衛生管理」だそうです。
綺麗に管理された蔵内が印象的でした。
酒米を蒸す作業所では、覗き込むと先ほど飲んだ仕込み水が流れ出ているのが見えます。
麹米の試食もさせてもらいました。 麴米を食べたのは初めてで、表面が少しほわっとしていて、噛んでいると甘みが出てきます。
さらに、少しだけ蔵人のお仕事の体験もさせてもらいました。
酒を上槽するためにタンク内に残った醪(もろみ)を綺麗にする作業。
手作業の部分が多くて、青木酒造の蔵人たちの酒造りへの丁寧さを実感しました。
その後、ビン詰め工程へ。
このビン詰め工程は先ほどとは一転、こちらはオートメーション化がされていて、まさしく工場といった雰囲気。
さらに蔵から移動して、国道17号の向かいの雪室倉庫へ。
牧之通りの街並みに見事に調和した外観で、歴史を感じさせる蔵です。
青木酒造は一般の方には酒蔵見学は実施していません。
写真も外部公開は不可ということなので、言葉に綴ります。
今回、酒の心は特約店契約をしていただいているので、特別に中を案内していただきました。
現在の蔵の方針は「徹底した衛生管理」だそうです。
綺麗に管理された蔵内が印象的でした。
酒米を蒸す作業所では、覗き込むと先ほど飲んだ仕込み水が流れ出ているのが見えます。
麹米の試食もさせてもらいました。 麴米を食べたのは初めてで、表面が少しほわっとしていて、噛んでいると甘みが出てきます。
さらに、少しだけ蔵人のお仕事の体験もさせてもらいました。
酒を上槽するためにタンク内に残った醪(もろみ)を綺麗にする作業。
手作業の部分が多くて、青木酒造の蔵人たちの酒造りへの丁寧さを実感しました。
その後、ビン詰め工程へ。
このビン詰め工程は先ほどとは一転、こちらはオートメーション化がされていて、まさしく工場といった雰囲気。
さらに蔵から移動して、国道17号の向かいの雪室倉庫へ。
牧之通りと同様に全体を囲むように雁木が設置されています。
2017年に竣工された雪室倉庫で、雪の利活用を通じた自然再生エネルギーで酒の貯蔵・熟成をしています。
2017年に竣工された雪室倉庫で、雪の利活用を通じた自然再生エネルギーで酒の貯蔵・熟成をしています。
大きな倉庫ですが、なんとここに大型除雪車を使い、めいっぱい雪を搬入するそうです。
中はとてもひんやり。
いや、ずっといたら寒いくらいにキンキンに冷えていました。
この雪室倉庫では雪を活用した日本酒の熟成に取り組んでいます。
雪で貯蔵することで、うまさが増す酒を熟成しています。
新酒とはまた違った角の取れたまろやかな旨みが生まれるんですね。
倉庫の奥には熟成された鶴齢が保存されていました。
雪国ならではの雪との共存、利活用をしています。
雪の力を肌で感じられる場所でした。
貴重な酒蔵見学と体験をさせてもらいました、ありがとうございました!
中はとてもひんやり。
いや、ずっといたら寒いくらいにキンキンに冷えていました。
この雪室倉庫では雪を活用した日本酒の熟成に取り組んでいます。
雪で貯蔵することで、うまさが増す酒を熟成しています。
新酒とはまた違った角の取れたまろやかな旨みが生まれるんですね。
倉庫の奥には熟成された鶴齢が保存されていました。
雪国ならではの雪との共存、利活用をしています。
雪の力を肌で感じられる場所でした。
貴重な酒蔵見学と体験をさせてもらいました、ありがとうございました!
青木酒造 直売所へGO!
さて、蔵に戻り、青木酒造の直売所にお邪魔しました。
中に入ると、直売所も酒蔵の中にあるので、同じく歴史的な蔵の趣と重厚感を感じます。
中に入ると、直売所も酒蔵の中にあるので、同じく歴史的な蔵の趣と重厚感を感じます。
青木酒造の代表銘柄は、鶴齢(かくれい)と雪男。
鶴齢は昔からある伝統銘柄で、地元民から根強く愛されている酒です。
一方で雪男は比較的新しい銘柄で、そのかわいらしい雪男のデザインから若者や女性からも人気が高い銘柄です。
雪男の売上の一部は山岳遭難防止対策へ寄付されます。
青木酒造の創業はなんと享保2年、西暦でいうと1717年!
300年以上もの間、酒造りをしているんですね。おどろきです。
鶴齢は昔からある伝統銘柄で、地元民から根強く愛されている酒です。
一方で雪男は比較的新しい銘柄で、そのかわいらしい雪男のデザインから若者や女性からも人気が高い銘柄です。
雪男の売上の一部は山岳遭難防止対策へ寄付されます。
青木酒造の創業はなんと享保2年、西暦でいうと1717年!
300年以上もの間、酒造りをしているんですね。おどろきです。
魚沼料理に合う「淡麗旨口」の酒造り
青木酒造のこだわりは「淡麗旨口」の酒造り。
新潟県といえば、「淡麗辛口」の酒が多いのですが、青木酒造では米の旨みを最大限に引き出した「淡麗旨口」の酒を醸すことをモットーとしています。
地元魚沼地域の食文化に合った酒造りをしているそうです。
豪雪地帯ならではの冬の間も長期保存が可能な干物や漬物と、醤油や味噌を使った料理が多い魚沼料理。
鶴齢はそれらの魚沼料理に合うような、淡麗を基準としながらも米の旨みを引き出し、料理との相性を考えた酒です。
酒によって料理も一層おいしく感じる、料理によって酒も一層おいしく感じるといったところでしょうか。
昔から地元民に愛される理由は、そういったところにあるわけです。
新潟県といえば、「淡麗辛口」の酒が多いのですが、青木酒造では米の旨みを最大限に引き出した「淡麗旨口」の酒を醸すことをモットーとしています。
地元魚沼地域の食文化に合った酒造りをしているそうです。
豪雪地帯ならではの冬の間も長期保存が可能な干物や漬物と、醤油や味噌を使った料理が多い魚沼料理。
鶴齢はそれらの魚沼料理に合うような、淡麗を基準としながらも米の旨みを引き出し、料理との相性を考えた酒です。
酒によって料理も一層おいしく感じる、料理によって酒も一層おいしく感じるといったところでしょうか。
昔から地元民に愛される理由は、そういったところにあるわけです。
地元民に愛される酒「鶴齢」 青木酒造の酒蔵巡り
今回は南魚沼市塩沢にある「鶴齢」醸造元、青木酒造を訪れました。
酒蔵を訪れることで、地元民に愛される鶴齢のこだわりが実感できる旅となりました。
その酒蔵のこだわりを直接聞け、その酒蔵の雰囲気を肌で感じられる酒蔵巡り。
酒蔵を訪れるからこそ五感で酒造りを感じられます。
さらに酒蔵の独特な雰囲気と香りがあいまって、酒がまたひとしおおいしく感じられます。
日本酒王国の新潟には、まだまだ私が訪れたことのない酒蔵がたくさんあります。
次はどこへ行こうか、、、
ではまた次回お楽しみに!!
酒蔵を訪れることで、地元民に愛される鶴齢のこだわりが実感できる旅となりました。
その酒蔵のこだわりを直接聞け、その酒蔵の雰囲気を肌で感じられる酒蔵巡り。
酒蔵を訪れるからこそ五感で酒造りを感じられます。
さらに酒蔵の独特な雰囲気と香りがあいまって、酒がまたひとしおおいしく感じられます。
日本酒王国の新潟には、まだまだ私が訪れたことのない酒蔵がたくさんあります。
次はどこへ行こうか、、、
ではまた次回お楽しみに!!

青木酒造
■住所:〒949-6408 新潟県南魚沼市塩沢1214
■創業:享保2年(1717年)
■特徴:地元民に昔から愛される酒、鶴齢を醸す。日本酒造りに最適な冬期間に仕込み、雪の恵みと越後杜氏の伝統の技を取り入れた正統蔵。
■代表銘柄:鶴齢(かくれい)、雪男
■酒蔵見学:実施なし
この記事を書いた人
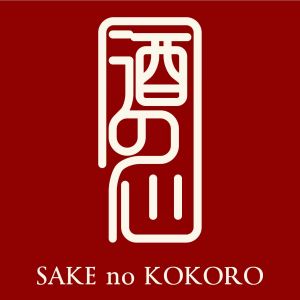
【年間400種類以上試飲している唎酒師が唸るうまい酒を紹介】
EC酒店「酒の心」代表+1児1歳の父 日本酒を通じて新潟の魅力を発信していきます! 子どもがおおはしゃぎする子育て世代へのおすすめスポットも紹介していきます。
■酒の心HP:https://sakenokokoro.com/

































