「手掘り中山隧道」でたどる村人の情熱と「えびすや」で味わう二八蕎麦/長岡市
2025年11月08日
いいね
3781ビュー
16年もの歳月をかけて、人の手、つまりツルハシで少しずつ掘られて完成したトンネルがあります。いまでもツルハシの跡が当時のまま残り、昔の人々のエネルギー、そして生きる力の大きさを感じさせる場所です。(※注:1937年に始まった日中戦争の影響で、1943年に作業は中断。戦後の1947年に再開され、約4年間の中断期間を含めて16年間の歳月がかかりました。)
この「中山隧道(ずいどう)」は、長岡市山古志の小松倉と魚沼市の水沢新田をつなぎます。当時、村人たちは中山峠を越えて行き来していました。冬には積雪が4メートルを超える地で、危険な峠越えを避け、魚沼方面へ安全に行けることは村人たちの悲願でした。
平成10年(1998年)に「中山トンネル」が完成したことで中山隧道は閉鎖されましたが、現在では入口の一部が見学可能です。
この「中山隧道(ずいどう)」は、長岡市山古志の小松倉と魚沼市の水沢新田をつなぎます。当時、村人たちは中山峠を越えて行き来していました。冬には積雪が4メートルを超える地で、危険な峠越えを避け、魚沼方面へ安全に行けることは村人たちの悲願でした。
平成10年(1998年)に「中山トンネル」が完成したことで中山隧道は閉鎖されましたが、現在では入口の一部が見学可能です。
中山隧道を訪れた後は、蓬平温泉へ。食堂と土産物店を兼ねた「えびすや」で二八蕎麦をいただきました。観光の楽しみは、やっぱり地元の美味しいものを味わうことですね。中山隧道から蓬平のお店までは約15キロ、車で30分ほどの距離です。
16年もの歳月をかけて完成させた手掘りのトンネルへ
見学可能エリアは山古志側の小松倉です。写真の左側に「中山トンネル」が通り、右側に「中山隧道」があります。広い駐車場があり、停めやすかったです。
現在(2025年)から約27年前の平成10年(1998年)に完成した「中山トンネル」。
現在から約92年前の昭和8年(1933年)から昭和24年(1949年)までかけて掘削して出来た「中山隧道」。
トンネル貫通時の記念撮影でしょうか。トンネルの入口付近に貼ってあった古写真です。パンフレットによると、昔から山古志には水を確保するために横井戸を掘る技術があり、それゆえに手掘りできたと言われているそうです。
見学可能エリアは入口から70メートル地点までとなっています。それでは、トンネルの中へ入って行きます。
トンネルの説明パネルや、土木学会選奨土木遺産選定の関連物、記録映画『掘るまいか』についてなど、掲示してあります。
ツルハシで岩を掘る!
ツルハシで岩を掘るなんて、想像するだけでも大変そうです。実際、平成10年(1998年)から撮影が開始された記録映画『掘るまいか』の再現シーンでは、硬い岩盤を砕くことができずに火薬を使用したそうです。
ツルハシの先が削れていくのを直しながら来る日も来る日も、2人1組になって硬い岩盤を打ち砕いたのだそうです。パンフレットの証言には「戦後の食糧難のなか、掘り手の父親の弁当にだけ、白いご飯が入っていました。どこの家もそうでした。それだけ、みんなの期待がかかっていたのです。」と書いてありました。
小松倉入口から440メートル地点、つまりトンネルの大体半分くらいの所で、大量出水が起きました。見学可能エリアの70メートル手前くらいでも水が滴り落ちていました。
見学可能エリアは70メートル地点まで
この先へは進めず、柵で閉鎖されていました。ここで折り返しになります。
柵の先をフラッシュを点灯して撮影しました。天井など、かなりボコボコしているのが見えます。
入口方面に振り返ると、左手に穴があり、トロッコが置いてありました。
トロッコが台形なのは木枠を楽に外して土を出しやすくするためとのことです。トロッコは、外からの空気を運び込む役割もありました。
村人たちの苦労と情熱で出来たトンネル
峠越えの苦労を無くしたい。その願いと引き換えに差しだしたのは、16年間(実質は12年間)の苦労でした。当時、山古志の男性は冬に出稼ぎへ行きましたが、隧道掘りが行われたのも冬。出稼ぎに行けない分、生活は苦しくなったのだそうです。
「やっぱり無理んがだすけ、止めようや。」とならなかった、村人の情熱。現在の私たちからすると、信じられないような、切実なる思いです。
「やっぱり無理んがだすけ、止めようや。」とならなかった、村人の情熱。現在の私たちからすると、信じられないような、切実なる思いです。
94才の小林守雄さんが語る、隧道の思い出
旧堀之内市(現在の魚沼市)竜光の小芋川村(現在は廃村)出身の小林守雄さんは昭和6年生まれで、現在(2025年10月時点)94才です。小芋川村は、中山隧道から直線距離で3~4Kmほどの位置にあります。
守雄さん「トンネルが開いた年、俺は、はたち前くらいだったかな(調べると18才)。母親の実家が水沢で、夏祭りで泊まりに行ったときに通った(貫通したのは5月)。中は、真っ暗だった。明かりなんて無かったから、手を横に上げてトンネルの壁を撫でながら行けばいいって言われてそうしたけど、だんだん手が下がってくるから壁にぶつかっちゃうんだ。」
シバゴー「人にはぶつからなかったんですか?」
守雄さん「歩く音が響くすけ、人が来るてがは分かった。」
シバゴー「全然明かりがなかったわけですよね。真っ暗闇の中を歩くのは怖くなかったですか?」
守雄さん「真っ暗だんだんが、戻ろうかと思いしまに(=思いながら)進んだ。長いと感じたね。あの頃は1キロあると聞いていた。手掘りであれだけ長いトンネルなんて、他所には無いね。たいしたもんだ。」
写真は、守雄さんが大変にお気に入りの「にこにこひろば」にて。「夜、寝るときに目を閉じると、あのきれいな風景が、まぶたに浮かんでくる。年をとったら歩かんなくなったすけ、行かれない場所も増えたけど、ここは車を停めたらすぐ、きれいな風景が見られる。本当に、いい場所だ」と話していました。
守雄さん「トンネルが開いた年、俺は、はたち前くらいだったかな(調べると18才)。母親の実家が水沢で、夏祭りで泊まりに行ったときに通った(貫通したのは5月)。中は、真っ暗だった。明かりなんて無かったから、手を横に上げてトンネルの壁を撫でながら行けばいいって言われてそうしたけど、だんだん手が下がってくるから壁にぶつかっちゃうんだ。」
シバゴー「人にはぶつからなかったんですか?」
守雄さん「歩く音が響くすけ、人が来るてがは分かった。」
シバゴー「全然明かりがなかったわけですよね。真っ暗闇の中を歩くのは怖くなかったですか?」
守雄さん「真っ暗だんだんが、戻ろうかと思いしまに(=思いながら)進んだ。長いと感じたね。あの頃は1キロあると聞いていた。手掘りであれだけ長いトンネルなんて、他所には無いね。たいしたもんだ。」
写真は、守雄さんが大変にお気に入りの「にこにこひろば」にて。「夜、寝るときに目を閉じると、あのきれいな風景が、まぶたに浮かんでくる。年をとったら歩かんなくなったすけ、行かれない場所も増えたけど、ここは車を停めたらすぐ、きれいな風景が見られる。本当に、いい場所だ」と話していました。
積雪期には除雪をしませんので立ち入りできません。ぜひ、積雪期以外に訪れて、先人たちがトンネル掘りにかけた情熱を感じてみてはいかがでしょうか。

中山隧道
【住所】長岡市山古志東竹沢(小松倉集落)
【アクセス】長岡南越路スマートICまたは小千谷ICより約20km(車で約25分)
食堂と土産物店を兼ねた蓬平の「えびすや」へ
山古志の手掘りトンネル「中山隧道」を訪れた後は、食堂と土産物店を兼ねた「えびすや」へ行きました。中山隧道からお店がある蓬平まで約15キロ、車で30分ほどの距離です。山道の風景が美しく、「きれいだね~」と言いながら運転していると、あっという間に山古志を通り過ぎて、「えっ、もう蓬平?」と思いました。
実は今回、中山隧道の取材を考えてからランチどうしよう、という流れでした。やっぱり観光したら、美味しいものを食べて帰りたいじゃないですか。「多菜田」は美味しいけど、前回に訪れたし、他に…と探して「えびすや」を見つけたのです。
実は今回、中山隧道の取材を考えてからランチどうしよう、という流れでした。やっぱり観光したら、美味しいものを食べて帰りたいじゃないですか。「多菜田」は美味しいけど、前回に訪れたし、他に…と探して「えびすや」を見つけたのです。
高龍神社の麓!ぜひ参拝も併せて。
写真、えびすやの右手にトンネルが見えますが、その上に、神社の本殿へ上がる階段とエレベーターの建物があります。長くて急な階段です。
ゆるく使った布海苔と二八蕎麦。
へぎ蕎麦2人前と天ぷら盛り合わせを注文しました。店主は中村冨美雄さん。ずっと土産物屋を営業していた後、昭和47年(1972年)に食堂を開店。冨美雄さんが50年以上、蕎麦を打っていらっしゃるそうです。現在は息子さんも一緒にされています。
蕎麦は「二八(にはち)」。蕎麦粉と小麦粉の配合割合を「8:2」の割合で混ぜて打った蕎麦のことです。へぎ蕎麦は「布海苔」を使いますが、冨美雄さん曰く「うちは、ゆるく使っています」。
蕎麦は「二八(にはち)」。蕎麦粉と小麦粉の配合割合を「8:2」の割合で混ぜて打った蕎麦のことです。へぎ蕎麦は「布海苔」を使いますが、冨美雄さん曰く「うちは、ゆるく使っています」。
シバゴー「ゆるく…?なぜ、ゆるく使うんですか?」
冨美雄さん「布海苔が強すぎると、蕎麦の香りがしなくなると思って、ちょうどいい塩梅をみて、ゆるく使っています。」
シバゴー「なんとなく、布海苔をたっぷり使った方が美味しいかなと思い込んでいました。」
冨美雄さん「布海苔が強いと、のど越しはいいんですけどね。」
シバゴー「蕎麦粉も十割の方が、より美味しいのかなと思ったんですけど、そうとも限らないんでしょうか。」
冨美雄さん「好みになりますけど、うちは、食べやすいのがいいと思って二八で提供しています。」
冨美雄さん「布海苔が強すぎると、蕎麦の香りがしなくなると思って、ちょうどいい塩梅をみて、ゆるく使っています。」
シバゴー「なんとなく、布海苔をたっぷり使った方が美味しいかなと思い込んでいました。」
冨美雄さん「布海苔が強いと、のど越しはいいんですけどね。」
シバゴー「蕎麦粉も十割の方が、より美味しいのかなと思ったんですけど、そうとも限らないんでしょうか。」
冨美雄さん「好みになりますけど、うちは、食べやすいのがいいと思って二八で提供しています。」
「ゆるく」か~、なるほど~と思いながら食べてみると…。「美味しい!」と、すぐに感想の言葉が出ました。「ん~、あ、美味しい、美味しいね、うんうん。」とかでなくて、「美味しい!」と、一口目で。食べやすいのって、美味しいんだなあと、すごく納得したような気分になりました。
訪問は9月下旬で、天ぷらの盛り合わせには糸瓜(いとうり)もありました。金糸瓜(きんしうり)や素麺瓜(そうめんうり)とも言うそうで、噛むと繊維が細長くホロホロと崩れて、面白い食感。糸瓜の天ぷらとは珍しいなあと、美味しくいただきました。
店内は4人掛けの席が余裕をもって配置され、20人ほど座れます。
メニューは、こちら(令和7年9月末時点)。山菜は、ご自身で山に入り採って、塩漬けなど加工した物だそうです。輸入品の瓶詰めじゃないとはさすが、美味しそう。次回は、あたたかい山菜蕎麦もいいなと思いました。
高龍神社に参拝した記念でお土産品を、ぜひ
高龍神社へ参拝に来たのですから、ぜひお土産は「龍神もなか」を。バラでも売っていましたが、3個入りの箱は包装紙の龍と、金色で「高龍神社」と書かれているのがいいな~と思って、私はこちらを購入しました。
味噌饅頭と草餅も人気商品とのことでした。帰りの道中に食べようと草餅を購入しました。
ご家族みなさんで仲良く営業されている雰囲気に癒されました。高龍神社への参拝には、ぜひ併せて、えびすやにお立ち寄りいただくのがおすすめです。

えびすや
【住所】新潟県長岡市蓬平町甲1220
【電話】0258-23-2080
【営業時間/食堂】10:30~15:00(ラストオーダー14:30)※無くなり次第終了
【定休日】火曜・木曜
【駐車場】約15台
中山隧道と蓬平温泉にある「えびすや」
この記事を書いた人
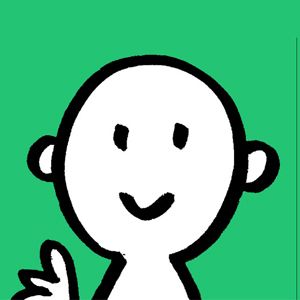
南魚沼市在住。趣味は写真撮影と読書で、本で調べた所へ行って写真を撮ることをライフワークとしています。神社彫刻が好きで、幕末の彫刻家・石川雲蝶と小林源太郎、「雲蝶のストーカー」を公言する中島すい子さんのファン。地域の郷土史研究家・細矢菊治さんや、地元を撮影した写真家・中俣正義さん、高橋藤雄さんのファンでもあります。













































