熱気あふれる「浦佐毘沙門堂の裸押合」。豪雪の地で行われる豊穣の祈り/南魚沼市
2025年04月04日
いいね
4789ビュー
「浦佐(うらさ)毘沙門堂(びしゃもんどう)の裸押合(はだかおしあい)」が3月1日(土)に開催されました。平成30年(2018年)国の重要無形民俗文化財に指定された伝統行事です。
「裸押合」の名の通り、参拝者たちがハンタコを履き、上半身裸で押し合いながら、堂内で撒かれる「福物」を得ようと奪い合い、秘仏の本尊を参拝しようと内陣の奥を目指します。
「裸押合」の名の通り、参拝者たちがハンタコを履き、上半身裸で押し合いながら、堂内で撒かれる「福物」を得ようと奪い合い、秘仏の本尊を参拝しようと内陣の奥を目指します。
歴史あるお寺の、古くからのお祭り。
今から約1200年前、坂上田村麻呂が御堂を建て、守護仏の毘沙門天王を祀って、部下の将士や村長・村人と共に国家安穏と戦捷を祈願し、あわせて五穀豊穣・家内安全・身体健康を祈り、祝宴の中で歌い、踊って士気を鼓舞したことに起因するものと言われています。(普光寺ホームページより)
毎月三のつく日(3日、13日、23日)は毘沙門天の祭礼市日で、とりわけ正月三日の裸押合いは、遠近からの大勢の参詣者がありました。(※1)明治以降に太陽暦になってからは、祭礼は三月三日に改められ(※2)令和2年(2020年)より、3月第1土曜日に変更となりました。
JR浦佐駅の西口からお寺へ向かいます。
JR浦佐駅の毘沙門天口(西口)を出て、5分ほど歩いて、普光寺の毘沙門堂へ向かいます。道路には両端に屋台が並んでいて、人出も多くにぎやかでした。
参道の入り口に「多聞天」の提灯が下がっています。
参道の「河田屋土産店」、その先の階段を上がると山門(仁王門)があります。
天保2年(1831年)に完成した山門。楼下の天井板には、谷文晁が描いたといわれる水墨の「八方ニラミの龍」がはめこまれており、『図解にいがた歴史散歩』執筆者で地域文化研究家の細矢菊治さんは「この下に立つと、いまにも竜が躍り出るかと思われるほどの力作」と書かれています。(※2)
こちらは別日の昼間、撮影した「八方ニラミの龍」。
いざ、毘沙門堂内の押合いを見学します!
参拝者たちは裸で押し合いながら、堂内で撒かれる「福物」を得ようと奪い合います。福物とは奉納物や縁起物を記した木製の撒き札や御盃のこと。この「福物撒与」は大祭の夜に三度、行われます。スケジュール表では、午後7時、午後8時、午後9時となっていました。
たくさん人が居る所を撮影しよう…と思いまして、あえて7時をしばらく過ぎてから、私は毘沙門堂へ行ったのですが、予想を上回る混雑で、見学者も押合い状態。すっかり人波にのまれてしまい、押合いしている所は見えませんでした。
たくさん人が居る所を撮影しよう…と思いまして、あえて7時をしばらく過ぎてから、私は毘沙門堂へ行ったのですが、予想を上回る混雑で、見学者も押合い状態。すっかり人波にのまれてしまい、押合いしている所は見えませんでした。
本尊を間近に参拝できる内陣によじ登ろうと突進。
私は事前に実行委員会へ取材申請していましたので、取材者専用の段に上がって撮影できました。
堂内の床より一段高い内陣には、青年団の内陣係が立ち並んでいます。内陣は、本尊の毘沙門天像正面の開口部以外、仕切りの板で閉ざされた状態。 開口部の前には内陣係が立ち並んでいるので、本尊は見えません。正面からよじ登って内陣に入れた参拝者のみ、本尊を間近に参拝できるのです。
堂内の床より一段高い内陣には、青年団の内陣係が立ち並んでいます。内陣は、本尊の毘沙門天像正面の開口部以外、仕切りの板で閉ざされた状態。 開口部の前には内陣係が立ち並んでいるので、本尊は見えません。正面からよじ登って内陣に入れた参拝者のみ、本尊を間近に参拝できるのです。
人馬に乗り、撒与品を記した白扇を捧げ持った撒与者の奉納。
大きなロウソクを抱えた人も、押合いの中に入ってきます。抱えた人の肩に、たっぷりとロウがかかっています…!
「さんよう、さんよ。さんよう、さんよ。」響き渡る、掛け声。
「撒くぞ撒くぞ」
「来い来い来いよ」
「さんよう、さんよ。さんよう、さんよ。」
掛け声が、堂内に響き渡ります。
たびたび水が、押し合う参拝者たちの背後や頭上から撒かれると、ブワッと湯気が立ちました。まだ雪がたっぷりとある三月初旬で、外気は十分に寒い。しかしながら、堂内は人間の体温のみで、暖かいを通り越し、暑いくらいの気温でした。人間のエネルギーというのはすさまじく、生きるとは尊いなあと思いました。
「来い来い来いよ」
「さんよう、さんよ。さんよう、さんよ。」
掛け声が、堂内に響き渡ります。
たびたび水が、押し合う参拝者たちの背後や頭上から撒かれると、ブワッと湯気が立ちました。まだ雪がたっぷりとある三月初旬で、外気は十分に寒い。しかしながら、堂内は人間の体温のみで、暖かいを通り越し、暑いくらいの気温でした。人間のエネルギーというのはすさまじく、生きるとは尊いなあと思いました。
雪の中の水行。これをしなければ押合いには参加できません。
参拝者は、「うがい鉢」で水行をしなければ押合いに加われません。顔の前で両手をあわせ「オン ベイシラ マンダヤ ソワカ」と真言をくり返し唱えます。
水行を終えて「さんよう、さんよ。さんよう、さんよ」と掛け声をかけながら、堂内を目指す参拝者たち。
「かっこいい祭りやなあ!」と歓声。
大祭の諸行事を支え、進行を担うのは浦佐多聞青年団。浦佐地区に在住する19才から29才までの男性が所属しています。
観光で訪れた人でしょうか、関西弁で「かっこいい祭りやなあ!」と感激している男性の声が聞こえました。
人間の生きる力ってすごい。豊作の年でありますように。
何メートルもの雪の中に埋もれるように暮らして、生きている魚沼の私たち。現在は除雪技術もあり、大変ではあるものの日常生活は春夏秋冬、比較的変わらず過ごしていられます。でも、ひと昔前まで、積雪期は冬眠するように、じっと耐えて過ごしてきたのでしょう。陽も差さず、暗い天候が続く中、雪に埋もれて。
押合いのエネルギーを目の当たりにすると、人間の生きる力ってすごいなあ。冬にはじっとしていても、春になれば、田んぼの苗がどんどん育つように、人間も生命力あふれて活動するんだなあと思いました。
どうぞ豊作の年でありますように。豊かな実りで、みんなが幸せに暮らせますように。そんな祈りが、祭り全体を覆っているように感じました。
押合いのエネルギーを目の当たりにすると、人間の生きる力ってすごいなあ。冬にはじっとしていても、春になれば、田んぼの苗がどんどん育つように、人間も生命力あふれて活動するんだなあと思いました。
どうぞ豊作の年でありますように。豊かな実りで、みんなが幸せに暮らせますように。そんな祈りが、祭り全体を覆っているように感じました。
これは文字で読まれるよりも、参拝者たちの「さんよう、さんよ。さんよう、さんよ」という声を聞いていただいた方が実感されるのではと思います。私は感動して、涙ぐんでしまいました。
押合いの参加は、男性なら誰でもできます。私が男性なら、一生に一度くらいは参加したかったと思います。せっかく男性に生まれた方は、ぜひ参加してみてください。そして、女性の我々も、目の当たりにするだけでもご利益があるように思います。ぜひ訪れてみてください。
(※1)『大和町の近世』(令和元年、南魚沼市教育委員会発行)
(※2)『図解にいがた歴史散歩』(昭和58年、新潟日報事業社出版部発行)
(参考)『浦佐毘沙門堂の裸押合の習俗 総合調査報告書』(平成21年、南魚沼市教育委員会発行)
押合いの参加は、男性なら誰でもできます。私が男性なら、一生に一度くらいは参加したかったと思います。せっかく男性に生まれた方は、ぜひ参加してみてください。そして、女性の我々も、目の当たりにするだけでもご利益があるように思います。ぜひ訪れてみてください。
(※1)『大和町の近世』(令和元年、南魚沼市教育委員会発行)
(※2)『図解にいがた歴史散歩』(昭和58年、新潟日報事業社出版部発行)
(参考)『浦佐毘沙門堂の裸押合の習俗 総合調査報告書』(平成21年、南魚沼市教育委員会発行)

別当 吉祥山 普光寺
【住所】南魚沼市浦佐2495
【拝観受付】午前9時30分~午後4時30分
【拝観料】お問合せください(境内は自由に拝観できます)
【電話】025-777-2001(要予約)
別当 吉祥山 普光寺
この記事を書いた人
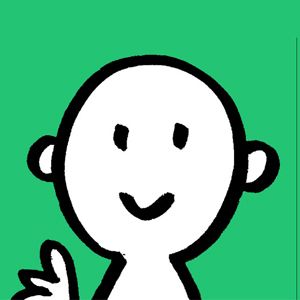
南魚沼市在住。趣味は写真撮影と読書で、本で調べた所へ行って写真を撮ることをライフワークとしています。神社彫刻が好きで、幕末の彫刻家・石川雲蝶と小林源太郎、「雲蝶のストーカー」を公言する中島すい子さんのファン。地域の郷土史研究家・細矢菊治さんや、地元を撮影した写真家・中俣正義さん、高橋藤雄さんのファンでもあります。




































